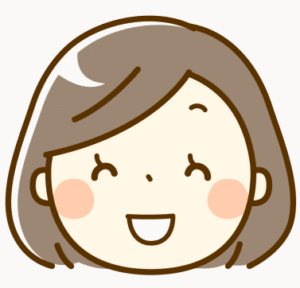
2月3日は節分だねぇ♪


なんで2月3日は節分なの?



えっ…



(曇りなき眼で見つめる)


えーっと、それは…
これは我が家で実際にあった話なのですが、当時は「ひゃっ!」ってなりました(汗)
いや、全然考えてなかった・・・
なんか、鬼さんがくるんだよーとか何とか、適当にごまかした覚えがあります・・・
現在6歳と3歳になった娘たち。
きちんと説明しないと納得しないだろうし親の沽券に関わるし、下の娘もまだ3歳とはいえ、正直うるさいししつこい(汗)・・・。
今年は去年のように簡単にはだまされてくれないだろーなー。
というわけで今回は、2月3日が節分なのはなぜなのか?
今回はその理由をバッチリ調べてまとめてみました!
子供向けの説明も最後に用意してありますので、ご覧ください♪
なぜ中途半端な日なんだろう?
2月3日が節分の理由は実は!ジャジャーン!
・・・といきたいところですが、節分についてお話した方が理由がわかりやすく、スッと頭に入ってきやすいようです。
というわけでまずは、『節分』についてお話していきますね!
節分とは?
節分とは、書いた字のごとく『季節を分ける』という意味を持ちます。
日本には『春夏秋冬』季節が4つあります。それぞれ、

● 夏の始まりの日『立夏(5月6日頃)』
● 秋の始まりの日『立秋(8月7日頃)』
● 冬の始まりの日『立冬(11月8日頃)』
となります。
節分とはつまり、一つの季節の終わりの日であり、次の季節に移り変わる節目の日(の前日)を指すんですね。
日本には季節が4つありますので、節分は正確には4回あるんです。
それぞれ、春の節分、夏の節分、秋の節分、冬の節分です。
ではなぜ、春の節分だけ《節分》と言われ、節分といえば2月3日!と定着しているのでしょう。
その理由は・・・
春だけ特別扱いされているのは
それはズバリ、2月3日の次の日、立春がとても大切にされていた日だからです。
昔の暦では、1年は立春から始まるとされていました。
1年が立春から始まるとなると、現在でいうところの、
● 立春=『元日』
● 立春の前日(節分)=『大晦日』
- 『1月1日』ではなく『元日』です。
現行の太陽暦では新年というと1月1日、立春は2月4日(頃)ですが、旧暦の立春(=新年)は毎年日にちにズレがあったようです。
このため立春は『元日』にあたるとの解釈の方がわかりやすいようです。
(元日とは、新年の最初の日です)
春を迎えるというのは新しい年を迎えることでもあり、新年を迎えるというのは最も重要なことでありました。今もですよね。
お正月のお祝いを表す賀詞に『迎春』という言葉があるのも、ものすごく納得いきました。1月1日は春じゃないだろー!って思ってました私(;’∀’)

この場合はそのものズバリ、新年を指しています。
迎春は友人などに贈る年賀状の賀詞として相応しい言葉とされています。
昔は、季節の変わり目には悪いものが入って来やすいと考えられていました。そして季節の変わり目以上に邪気が入りやすく、重要視されてきたのが年の変わり目でした。つまり立春の前日。春の節分です。
春の節分は旧暦では大晦日に相当するとされる日であり、悪いものを祓い、新年に福を呼び込むためのさまざまな行事を行う日でもありました。
『鬼は外~!福は内~!』 2月3日節分。 定番の掛け声と共に、なぜか撒かれる豆!豆!豆! 豆まきの豆って固いからぶつけられると痛いし(我が家では当然、鬼は夫の役目です笑)、豆まき後の裸で落ちてる豆、これを拾って食べるのー …
このように1年に4回ある節分の中でも、年の変わり目である春の節分・立春が大変重要とされ、現在(太陽暦)では節分というと立春の前日、2月3日を指すようになったと言われています。
簡単な説明






2月3日の節分は、昔のカレンダーでは冬の最後の日だったんだよ。


えっ、2月3日が?






そうなの。
冬が終わると、春がくるよね?



うん!
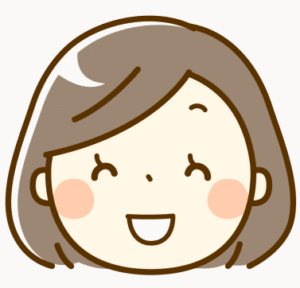
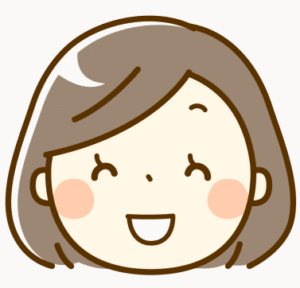
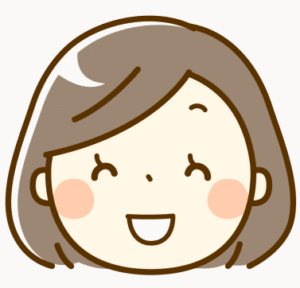
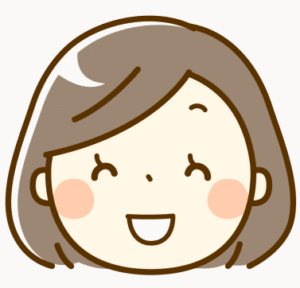
昔の人は暖かい春をとっても大事にしていたんだ。
節分は『これから良い事がたくさんありますように』って、悪い鬼をやっつける日なんだよ。



そうなんだ!



???



え、ええと…



?






あったかくなった時に鬼が出ないように、やっつける日だよ!



…。






…。


おにがでるの!?






鬼が出るの…


やだー、やっつける!!!
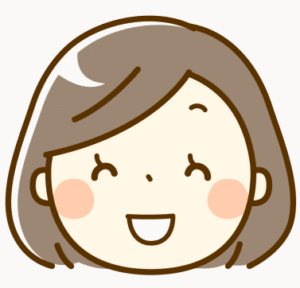
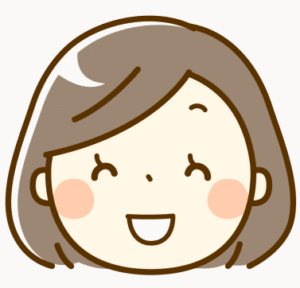
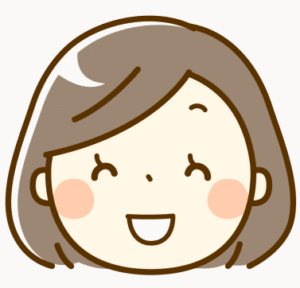
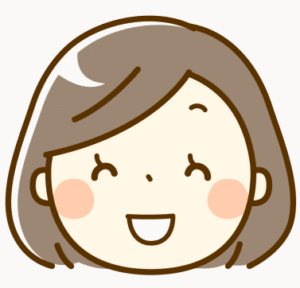
…ぜひそうして!!
こんな感じでいかがでしょう。
それでもまだ何か突っ込まれそうですが^^;
(3歳児にわかるように説明するのってムズカシイ~)
後記
● 節分
季節の分け目の日。春夏秋冬で4回ある。
● 2月3日が節分の理由は
昔の暦の『元日』にあたる立春が、現在の暦では2月4日のことが多く、その前日の2月3日が節分では1番大切にされていたから
節分が2月3日である理由を調べてみましたが、『春の節分』に思っていた以上に重要な意味があってビックリしました。
現在では、家庭ではお父さんやお母さんが鬼の役をして子供が豆を投げて楽しむ、というイベント的な行事になっていますが、楽しみながらもきちんと意味があること、子供に伝えていきたいなと思いました。

